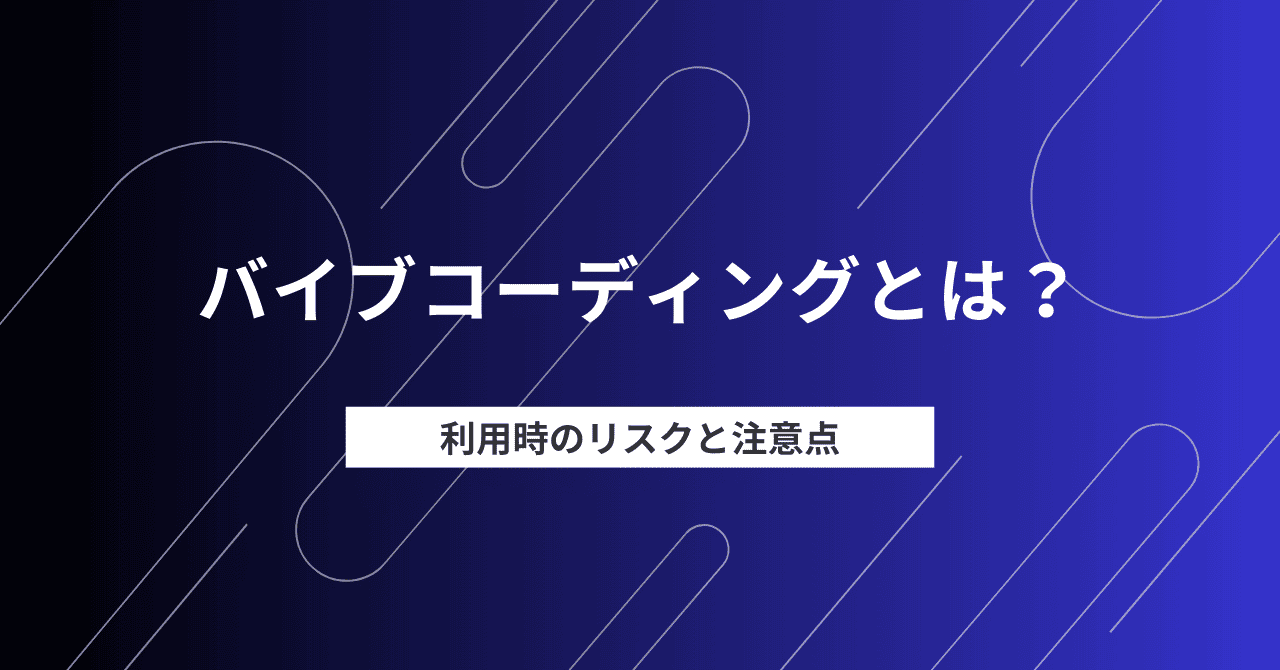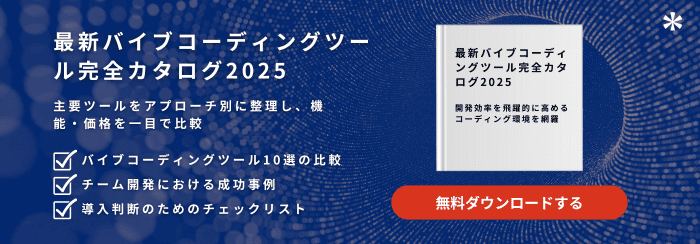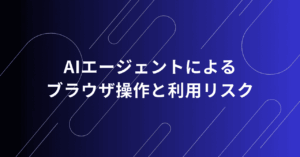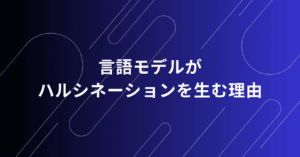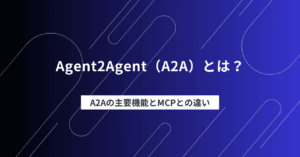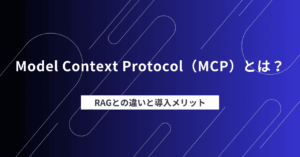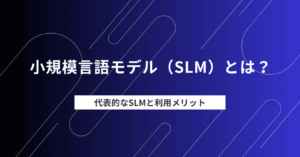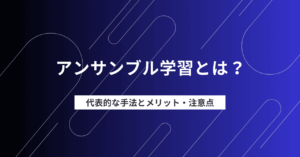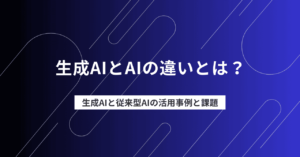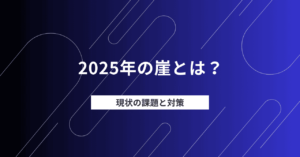バイブコーディングとは、実現したい機能や前提を文章で伝え、AIがコード全体を下書きし、人が動作を確かめて修正指示を重ねる開発手法です。ノーコードやローコードより設計の自由度が高く、従来の手書きより試作までの時間を短くできます。開発者は意図と受け入れ基準の言語化に集中し、AIは実装と改良を担います。
一方で、ドキュメント不備やセキュリティ設定の甘さが課題になりやすく、Next.jsとSupabaseの直アクセスやRLS未設定は情報漏えいの誘因になります。速度と安全の両立には、記録、レビュー、権限制御の運用が欠かせません。
バイブコーディングとは
バイブコーディングは、実現したい機能や前提条件を記述し、生成AIが提示するコード案を材料に、人が動作確認と改良指示を重ねて仕上げていく開発スタイルです。ノーコードやローコードより設計の自由度が高く、従来の手書きコーディングより着手が容易になります。基礎的なプログラミング理解があると安定した成果になりやすく、発想の検証や小規模ツールの作成で強みを発揮します。
背景には、ChatGPTやClaude、Geminiなどの汎用モデルと、CursorやGitHub Copilotのような支援ツールの進化があります。要件の言語化に人の時間を配分し、実装の初稿作成をAIに任せることで、試作から学びを得るまでの時間を短縮できます。
開発の形式
バイブコーディングには大きく2つの開発の形式があります。
1つ目は探索重視です。バイブコーディングの探索重視では、短時間で動くものを作ることを最優先にし、AIの提案を広く受け入れて試作品を素早く反復します。得られた気づきを次の指示に反映し、価値や方向性の見極めを進めます。週末の小規模プロジェクトや社内向けの簡易ツール、仮説検証の初期段階と相性が良い進め方です。
2つ目は実務重視です。バイブコーディングの実務重視では、生成コードのレビューやテスト計画、依存関係と権限の確認、ログ設計を人が主導します。認証基盤や実績のあるライブラリを優先し、静的解析や脆弱性点検といった工程を組み込みます。熟練者は設計と検証に注力し、非エンジニアは要件整理と受け入れ基準の明確化を担って協働します。開発速度は保ちつつ、品質と安全性の責任は最終的に人が負います。
従来手法との違い
従来の開発は、コードが主要な入力であり、開発者が言語仕様やAPIを正確に記述して積み上げます。バイブコーディングは、目的、前提、制約、期待する挙動といった文章が主要な入力になり、AIがその記述をもとに初稿のコードを生成します。入力の単位がコードから文章へ移るため、企画段階の判断材料が早い段階で可視化しやすくなります。
工程の焦点も変わります。従来は設計・実装・デバッグの比重が実装側に偏りがちです。バイブコーディングでは、プロンプト設計と結果評価に時間を配分し、初稿生成をAIに任せます。先に全体像の叩き台を得て、差分指示で形を整えるため、価値の有無や優先順位を早く判断できます。ただし、規制や信頼性要件が厳しい領域では、叩き台の段階で過信せず、レビューとテストを厚く設計する姿勢が不可欠です。
品質と保守の考え方も異なります。従来は実装者の理解とテスト設計が品質の中核になります。バイブコーディングでは、AI出力のばらつきを前提に、受け入れ基準や検証手順を先に定め、ログや計測で挙動を観測可能にします。保守ではコミット履歴だけでなく、プロンプトや前提条件、モデルやツールのバージョンといった生成履歴を管理し、再生成可能な形で差分を積み上げる運用が重要になります。結果として、非エンジニアを含む関係者が要件記述や受け入れ基準を共有しやすくなり、合意形成の速度と透明性が高まります。
バイブコーディングと他の手法の違い
従来のAI支援が入力補完や定型コードの提示にとどまりがちだったのに対し、バイブコーディングではAIが設計意図を読み取り、複数ファイルにまたがる構成やリファクタリングまで踏み込む点が特徴です。用語の普及にはアンドレイ・カーパシーの発信が影響しました(OpenAIの初期メンバー、元TeslaのAI担当)。開発者はキーボード操作よりも意図の言語化と受け入れ基準の設定に時間を使い、AIは実装の初稿と改良の反復を担います。
AIペアプログラミングとの違い
AIペアプログラミングは、人間が主導してコーディングを行い、AIは隣で助言や短い提案を返す関係になります。コードを入力する主体は人間で、AIはレビュー相当の示唆や次の一手の補助を行います。バイブコーディングは発想が逆で、AIが実装の主体となり、設計の補完や構成変更まで担当します。開発者は作りたい機能、前提、品質条件を明確に述べ、結果を検証して追加指示を与えます。人がハンドルを握り続けるか、AIに運転を任せて人が行き先と合格基準を示すかという運転権限の違いが本質です。
GitHub Copilotとの違い
GitHub Copilotは、現在書いている行や周辺コンテキストを読み取り、次に続くコードやテンプレートを提示する補完ツールです。入力効率が上がり、ボイラープレートの削減に強みがあります。バイブコーディングは補完を超え、要件の文章から画面、ルーティング、データ処理、テストまでをまとめて生成し、結果を見て言い換えや追加条件で再生成を重ねます。Copilotがエディタ内の入力体験を加速するのに対し、バイブコーディングはプロジェクト全体を会話で動かす発想で、役割分担が実装補助から共同実装へと広がります。
バイブコーディングのリスク
バイブコーディングには生産性という利点がある一方で、設計検討が薄いままコード生成を進めるとセキュリティが置き去りになりやすいという弱点があります。AIは短時間で動作する実装を提示しますが、安全要件を過不足なく満たすとは限りません。結果として、個人情報の漏洩やアカウント乗っ取りにつながる不具合が発生します。
バイブコーディングとの関係
バイブコーディングでNext.jsやSupabaseは必須ではありませんが、画面・API・認証・ストレージを短時間でそろえられるため、試作段階で選ばれやすい組み合わせです。AIは公開チュートリアルや一般的な雛形を参考にコードを生成する傾向があり、開発速度を優先したクライアント直アクセス構成を提案する場面が増えます。採用頻度が高い分、設計を誤ると同種のリスクが繰り返し発生します。
Next.jsは画面とサーバ処理を一体的に扱えるフレームワーク、Supabaseは認証やストレージを備えたクラウドデータベースです。両者の組み合わせは短期間でWebアプリを構築できますが、ブラウザからSupabaseへ直接問い合わせる設計は危険性が高くなります。匿名公開キーでのクライアント直アクセスは実装が簡単で速度も出ますが、キーはブラウザの開発者ツールで取得可能です。キーを盗まれると、想定外の範囲でデータ取得や操作が行われる恐れがあります。安全性を確保するには、サーバ側経由のアクセス設計や厳格な権限制御が前提になります。
RLSが要になる理由
Supabaseのようなサービスは表形式でデータを管理し、各レコードを行として保持します。RLS(Row Level Security)は、行単位で「誰が読むか・誰が書くか」を制御する仕組みです。設定が不十分な状態では、正規の認証を通過した一般ユーザーでも他人の行に到達でき、全ユーザーの情報が一挙に露出します。結合を含む複雑なクエリでは条件の抜けや優先順位の誤りが起こりやすく、専門家でも慎重な設計が欠かせません。バイブコーディングで生成された初稿をそのまま採用すると、RLSが未設定または緩い状態で本番公開されるリスクが高まります。開発速度を保ちながらも、RLSを前提にしたアクセス設計と検証を人が主導する姿勢が不可欠です。
バイブコーディングを利用するときの注意点
バイブコーディングは開発速度を高めますが、誤った実装の混入、設計や変更の不記録によるブラックボックス化、ノウハウの属人化、複雑要件への対応限界という4つのリスクに注意が必要です。品質確認と記録の徹底、知見の標準化、適材適所の適用方針を組み合わせることで、安全に活用できます。
正しいコードが生成されるとは限らない
AIが出力するコードには、仕様の取り違え、例外や境界値の未処理、認可漏れや入力検証不足といった欠陥が含まれることがあります。生成物をそのまま採用せず、意図との突き合わせ、コードレビュー、単体・結合・E2Eテスト、静的解析や依存関係の脆弱性チェックを通して品質を確認してください。
設計書や変更履歴を残しておく
会話主体で作業が進むため、設計や意思決定の記録が後回しになりがちです。後工程の改修を容易にするため、要件、プロンプトと入出力例、採用・却下理由、モデルやツールのバージョン、生成日時、コミットIDを残します。READMEやアーキテクチャ図、決定記録、変更履歴の形でリポジトリに集約すると、ブラックボックス化を避けられます。
ノウハウが属人化しやすい
AIへの指示の書き方や検証の勘所が個人に偏ると、担当不在時に開発が止まります。プロンプトのテンプレート化、レビュー観点のチェックリスト化、再現手順や検証データの共有、プロンプトと結果の差分記録を標準運用に組み込み、誰でも同じ結果に到達できる状態を保ってください。
複雑なコーディングには限界がある
フォーム作成やデータのCRUDのような定型には強い一方で、厳密な一貫性、複雑な状態管理、規制対応、スケーラビリティが絡む領域では限界があります。プロトタイピングやPoCでは速度を優先し、本格導入では設計、セキュリティ、テスト自動化、運用監視を厚くする方針に切り替えると安全です。
最後に
バイブコーディングは、AIに実装を任せつつ人が判断を担う協働の設計です。探索重視では試作と学習を最速で回し、実務重視ではレビューやテスト、権限とログの設計で品質を守ります。従来手法との違いは、入力の中心がコードではなく文章になる点で、意思決定が可視化しやすくなります。反面、Next.jsとSupabaseの直アクセスやRLS不備などの脆弱性、記録不足や属人化、複雑要件への対応限界が課題です。価値検証は迅速に、本番運用は統制を前提に進める姿勢が安全です。