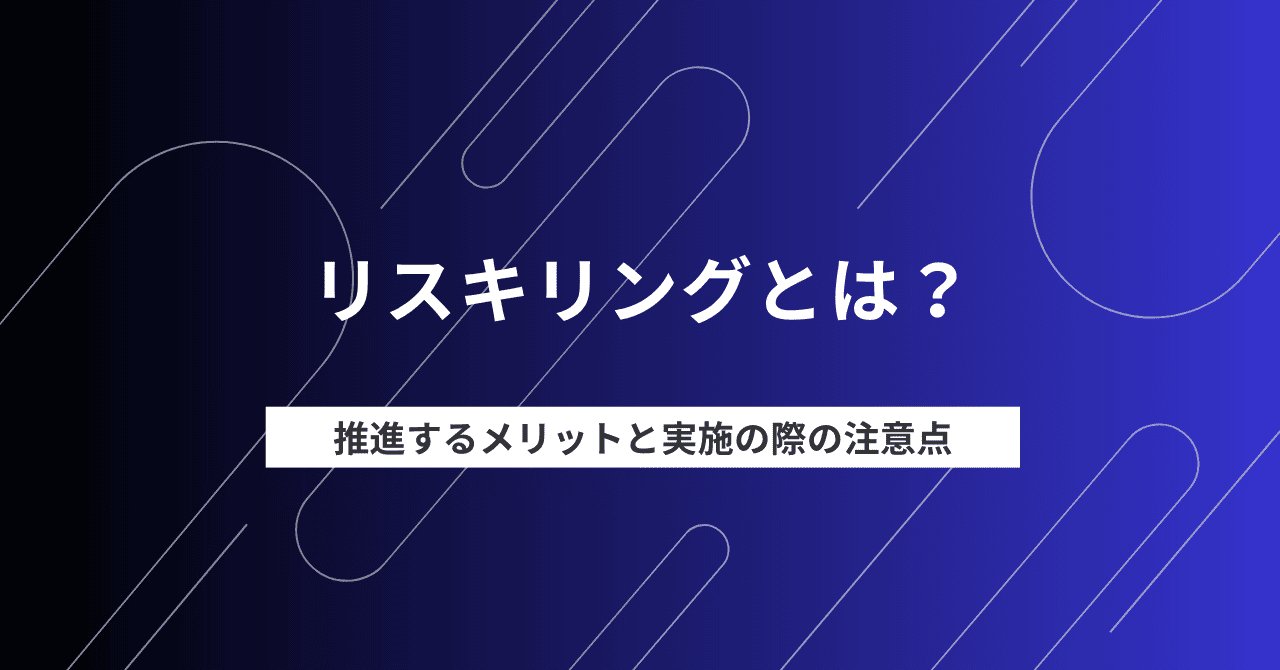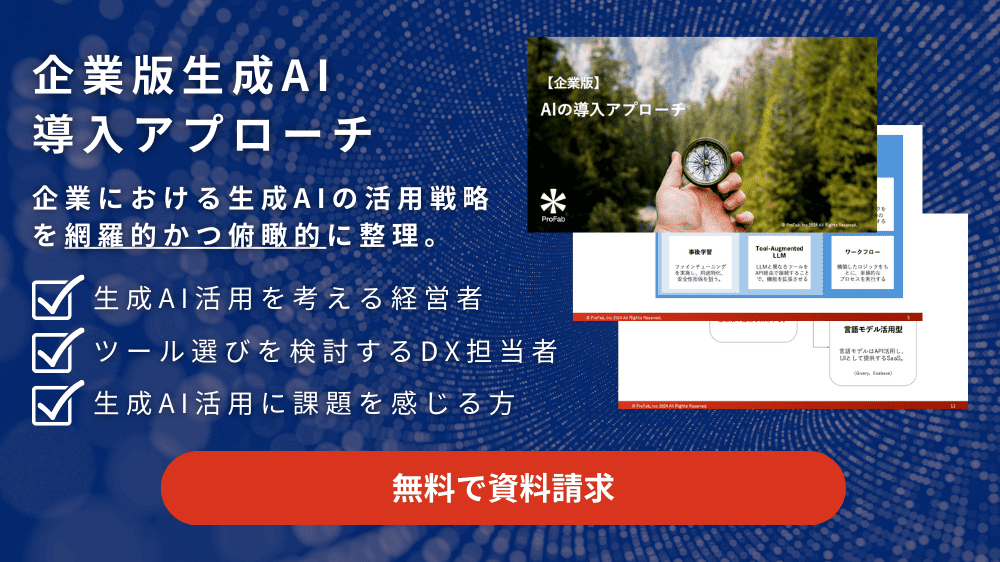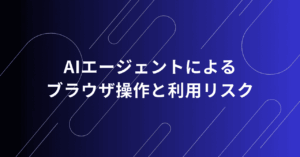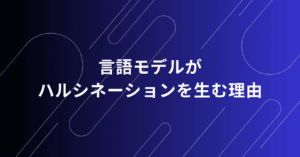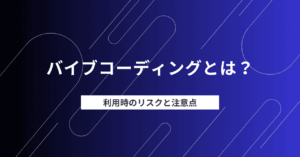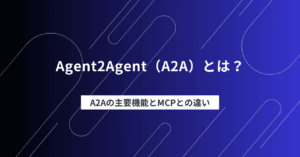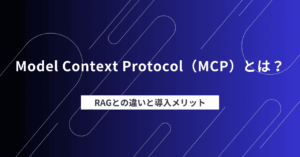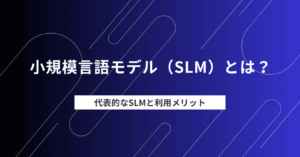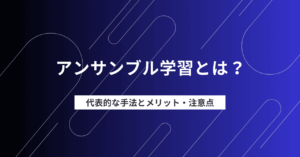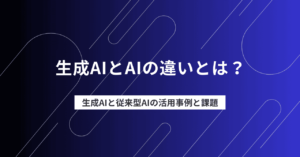リスキリングとは、新しい環境に適応するために必要なスキルを習得することを指します。技術革新やビジネスモデルの変化により、求められるスキルが大きく変わる中、継続的な学び直しが重要視されています。特にデジタルトランスフォーメーションが進むことで、新たな技術を活用できる人材の確保が課題となっています。
近年、世界的にリスキリングの必要性が高まり、政府や企業も積極的に取り組むようになりました。日本でも経済産業省がリスキリングを支援する施策を打ち出し、労働市場の変化に対応できる人材の育成を進めています。企業にとってもリスキリングを導入することで、業務の効率化や新規事業の創出、社員のキャリア成長を支援できるようになります。
リスキリングとは
リスキリング(Re-skilling)とは、新しい環境に適応するために必要なスキルを習得することを指します。企業が主体となり、従業員のスキルを再開発・再教育する場合と個人が主体的に取り組む場合があります。
技術革新やビジネスモデルの変化に対応するため、業務で必要となる新しい知識やスキルを学ぶことが目的とされており、経済産業省はリスキリングを「新しい職業に就くため、または現在の職業で求められるスキルの大幅な変化に適応するために必要なスキルを獲得する/させること」と定義しています。
リスキリングは必ずしもDX教育と同じ意味ではありませんが、特にDX化に対応するスキルの習得や、仕事の進め方が大きく変わる職種への適応を指すことが増えています。
社会の要請によって就業者のスキルが変化するため、企業が主体となることが多いものの、学ぶ本人の主体性も不可欠です。そのため「獲得する/させる」という双方の視点が併記されています。
リカレント教育との違い
リカレント教育は社会人が大学などの教育機関で学び直すことを指します。一方、リスキリングは企業が従業員に新たなスキルを習得させるため、研修や業務を通じて学習の機会を提供する点が異なります。
リカレント教育は個人が主体的にスキルアップを目的として学ぶことが多く、大学などの教育機関を利用しますが、リスキリングは企業が主体となり、業務に直結するスキルを習得させることを目的とする点が大きな違いです。
生涯学習との違い
生涯学習は人生を豊かにするために幅広い分野の知識を学ぶことを指します。学習の対象は、教育機関での学びだけでなく、スポーツ、ボランティア活動、文化活動、趣味など多岐にわたります。
リスキリングは、業務に必要なスキル習得を目的とするため、生涯学習とは学習の目的が異なります。
アンラーニングとの違い
アンラーニングは既存の知識や経験を捨て、新たな知識やスキルを習得することを指します。従来の方法が通用しなくなる環境では過去の知識やスキルのうち、時代に合わないものを意識的に手放し、新しいものを取り入れる必要があります。
リスキリングとアンラーニングは、新たなスキルを習得する点では共通しますが、アンラーニングは「古い知識を意識的に捨てる」ことが前提となる点が特徴です。
その他の学びに関する用語との違い
学びに関する概念には、アップスキリングやアウトスキリングもあります。
アップスキリング:現在の職務でキャリアアップするために、スキルや知識を向上させることを指します。
アウトスキリング:人員整理の対象となる従業員や、そのリスクが高い従業員に対し、デジタル分野などのスキル教育を実施し、成長産業へのキャリアチェンジを支援することを指します。
リスキリングが注目される理由
2020年に開催された世界経済フォーラムで「2030年までに地球人口のうち10億人をリスキリングする」と宣言され、欧米を中心にリスキリングが世界的な潮流となりました。日本でも経団連が2020年11月に発表した新成長戦略の中で、リスキリングの必要性について言及しています。
在宅勤務やリモートワークの普及、デジタル技術の進化、脱炭素化など、働き方や産業構造の変化に対応するため、日本政府もリスキリングに注目しています。経済産業省が2020年9月に公表した人材版伊藤レポートでは、人的資本経営を実現するための要素としてリスキル・学び直しを重要視しています。
さらに政府は、2022年にリスキリング支援として5年間で1兆円を投資すると発表しました。これを受けて、経済産業省は2023年に「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」を整備しました。この事業では、在職者に対してキャリア相談からリスキリング、転職支援までを一体的にサポートする仕組みを整え、民間企業の取り組みを支援しています。
特にDX(デジタルトランスフォーメーション)の加速によって、リスキリングの重要性がより一層高まっています。DXの推進には新たなスキルが求められるため、多くの企業が従業員のスキルアップを支援する必要性を感じています。
企業内におけるリスキリングの必要性
人的資本経営では人材を資本と捉え、従業員の知識やスキルを向上させることに投資することで企業価値や競争力の向上を目指します。特に、既存事業のデジタル化や新規事業の開発においてリスキリングは不可欠です。
企業がリスキリングを進める際には、まず目標とする状態と現状のギャップを明確にし、必要なスキルを洗い出すことが重要です。その上で、従業員が学ぶ時間を確保できるような業務スタイルを整え、評価基準や報酬体系を見直すことが求められます。
また、スキルの可視化や適材適所の配置を進めるために、タレントマーケットプレイスの導入も有効です。リスキリングが進めば生産性向上や新規ビジネスの創出が期待できるだけでなく、スキルを基準とした採用が可能になり、企業が必要とする人材を確保しやすくなります。
DXの進展とリスキリングの必要性
DXの進展に伴い、多くの企業が「人材不足」という課題に直面しています。単純に労働力が不足しているわけではなく、DXに必要な高度なスキルを持つ人材が不足しているのが現状です。そのため、新たな人材を採用するだけでなく、既存の従業員をリスキリングし、DXを支える人材に育成することが急務となっています。
また、AIの発展が大きな影響を与えています。ChatGPTのような生成AIの登場により、創造的な業務にもAIが活用されるようになっており、今まで安泰とされていた職種にも変化が求められ、企業はDX人材の確保や育成に力を入れています。
VUCA時代に対応するためのリスキリング
現代は変化が激しく、先行きが不透明な「VUCA時代」と呼ばれています。VUCAとは、以下の4つの要素の頭文字を取った言葉です。
- Volatility(変動性):顧客ニーズや価値観が急激に変化する
- Uncertainty(不確実性):外部環境や制度の変化が予測しにくい
- Complexity(複雑性):ビジネス環境が多様で複雑化している
- Ambiguity(曖昧性):明確な答えが存在せず、不確実性が高い
パンデミックの際には従来の働き方が通用せず、テレワークの導入や業務の転換が求められました。このように、予測できない変化に迅速に適応することが求められる時代では、決められた手順を踏めば成功できるという従来の考え方が通用しなくなっています。
VUCA時代に求められるのは柔軟に対応できるスキルと学び続ける姿勢です。時代の変化に応じて必要な知識や技術を習得し、新しいことに挑戦し続けなければ企業の成長は難しくなります。そのため、リスキリングを通じて、時代に適したスキルを継続的に習得することが重要です。
少子高齢化と個人のスキル向上の重要性
日本では少子高齢化が進み、労働人口が減少すると予測されています。総務省の資料によると、2025年には生産年齢人口(15~64歳)が2021年と比較して29.2%減少するとされています。
労働人口の減少は企業の人材不足を深刻化させ、事業の維持が難しくなる可能性があり、次のような課題が発生することが考えられます。
- 労働力の確保が難しくなる
- 採用競争が激化し、人材獲得が困難になる
- 限られた人材で生産性を向上させる必要がある
このような状況では、社員一人ひとりが多様な業務に対応できるスキルを持つことが求められます。リスキリングを通じて、適材適所の配置転換を進めるとともに、社内に不足しているスキルを身につけることが重要です。
これからの時代は、個人のスキルが企業の成長を左右するようになります。社員が自ら学び、適材適所で活躍することで限られた労働力の中でも高い成果を生み出せるようになるはずです。
企業がリスキリングを推進するメリット
リスキリングは企業の持続的な成長に貢献し、人材不足の解消や業務の効率化、イノベーションの促進につながる重要な取り組みです。企業が競争力を維持し、成長を続けるためには従業員のスキル向上を支援し、時代の変化に適応できる組織を構築することが欠かせません。
人材不足に対応できる
国内では事務職や生産職の余剰が数百万人規模で発生すると予測される一方で、デジタル人材をはじめとした専門職・技術職は同程度以上の人材不足が見込まれています。
DX人材を外部から採用することも1つの方法ですが、競争が激化しており、確保が難しい状況であるため、既存の従業員をリスキリングし、必要なスキルを習得させることは、企業にとって理にかなった選択肢といえます。
自律型人材を育成できる
企業がリスキリングを推進し、従業員に学びの機会を提供しながらキャリア形成を支援することで、エンゲージメントの向上につながります。エンゲージメントが高まると、従業員のモチベーションが向上し、生産性の向上や業績の改善が期待できます。
また、リスキリングの推進によって、従業員の中に「自分で新しいスキルを獲得しよう」という意識が生まれます。主体的に学び、成長しようとする自律型人材が増えることで、企業の組織文化も変化し、よりイノベーティブな風土が醸成されます。
既存人材が即戦力になる
リスキリングを実施した従業員は、企業の業務プロセスや文化に精通しているため、新しく習得したスキルをすぐに業務に活かすことができます。新たなスキルを持つ外部人材を採用する方法もありますが、社内の業務に適応するまでに時間がかかることが通常です。しかし、既存の従業員にリスキリングを行うことで即戦力として活躍できるようになります。
業務の効率化が期待できる
業務のデジタル化を進めることで作業の効率化や工数削減が可能になります。従業員が新たなデジタルスキルを習得し、業務に取り入れることで、より生産性の高い働き方が実現できます。削減した時間を企画業務や新しい役割に充てることで企業全体のパフォーマンス向上にもつながります。
また、リスキリングによって新しい技術や知識を身につけた人材が増えることで、新規事業の立ち上げやイノベーションの創出が期待できます。特に、DXやデータ活用が進む中で新たなビジネスチャンスを見出し、競争力を高めるためには、従業員が継続的に学び続けることが重要です。
企業文化が維持できる
企業が成長し続けるためには、組織の価値観や文化を維持しながら、新しい変化に対応することが求められます。外部人材の採用だけに頼ると、企業文化の一貫性が損なわれる可能性がありますが、既存の従業員をリスキリングすることで、組織の文化を守りながら変革を進めることができます。
採用コストが削減できる
DX人材の採用には高いコストがかかることが課題とされています。前職で高い専門性を持っていた人材でも、新しい企業の環境に適応できるとは限りません。
一方、既存の従業員にリスキリングを実施すれば、社内異動によって人材を充足できるため、採用コストを大幅に削減でき、デジタル化による業務効率化を進めることで余剰人材の発生を抑え、最適な人員配置を実現できます。
リスキリング導入のステップ
戦略に基づいた人材像やスキルを定める
リスキリングによって習得すべきスキルは企業の特徴や目標によって異なります。そのため、業績や事業内容のデータを参考にしながら、どのスキルを習得すべきかを明確にすることが重要です。データを活用する際にはデータベースやAIを活用することで、必要なスキルを効率的に洗い出せます。
リスキリングは手段であり、目的ではありません。経営戦略と連動した人材戦略を明確にし、その戦略を実現するために必要な人材像やスキルを特定することが必要です。
教育プログラムを決める
リスキリングに取り組む従業員が効率よくスキルを習得できるように、適切なプログラムを設計することが重要です。また、プログラムの構成や学習の順番にも注意が必要です。質の高い学習プログラムを用意しても学習の順序が適切でなければ、スキルの定着度が低下する可能性があります。
リスキリングの学習方法には研修、オンライン講座、社会人大学、eラーニングなどさまざまな選択肢があります。社内で対応できない場合は外部講師を招いたり、外部ベンダーの学習コンテンツを導入するのも有効です。学習方法を幅広く用意することで従業員が自分に合った学習方法を選択でき、学びの効果が高まります。
取り組みを開始する
プログラムと教材が準備できたら、従業員にリスキリングを実施します。学習の時間をあらかじめ決める方法や従業員が自由に学べる環境を整える方法など、企業の方針に応じた運用が求められます。
注意すべき点として、新しいスキルを習得することは従業員にとって負担やストレスを伴う場合があります。そのため、強制的に学ばせるのではなく、本人の意思を尊重することが大切です。1on1の面談などを通じて、本人のキャリア観とすり合わせながら学習を進めることで、モチベーションを維持しやすくなります。また、就業時間外の学習を推奨すると、従業員の意欲を削いでしまう可能性があるため、できるだけ就業時間内に学習の機会を設けることが望ましいといえます。
リスキリングしたことを実践で活かす
習得したスキルや知識を実際の業務で活用しなければ、リスキリングの効果を十分に発揮できません。そのため、学んだ内容を実務に応用できる場を提供することが重要です。学習したスキルを実際にどのように活かせるかを考えるために、業務の設計を見直すことも有効です。
さらに、学習した内容が定着するよう、実践後のフィードバックの機会を設けることが重要です。学び続ける環境を整え、スキルを継続的に磨くことで、企業全体の成長につながります。
リスキリング実施の際の注意点
必要なスキルを選定してから行う
リスキリングを実施する際には、まず従業員にどのスキルが必要なのかを明確にすることが重要です。事業戦略や将来の目標に基づき、習得すべきスキルを選定することで、リスキリングの効果を最大化できます。
社外のリソースを有効活用する
技術的なスキルやデジタルに関する基礎知識を習得するには、社内の研修プログラムだけでなく、外部サービスやコンサルティングの導入も有効です。特に、最新の技術やトレンドを学ぶためには、外部の専門家の知見を取り入れることが有益です。
リスキリングでは座学だけでなく、実際の業務課題に取り組む機会を設けることも大切です。理論だけでなく実践的なスキルを身につけることで、学んだ内容を業務に活かしやすくなります。
従業員へ説明をし、理解を促す
リスキリングに対して、「自分の仕事には関係ない」「ITのことは苦手」といった懸念を持つ従業員もいるかもしれませんが、企業はリスキリングの重要性を伝え、ネガティブな先入観を払拭することが求められます。
また、忙しいという理由で学習に消極的な姿勢を示す従業員も出てきますが、スキルを習得することで得られるメリットを具体的に伝え、モチベーションを維持できるように働きかけることが大切です。
社内の協力体制を整える
社内でリスキリングを推進するには、経営陣や他の従業員の理解と協力が不可欠です。経営陣に対してリスキリングのメリットを伝え、取り組みを支援してもらうことが大切です。
また、社内に賛同者を増やすことで、協力体制を強化できます。反対意見が多いとリスキリングの導入が難しくなるため、積極的にコミュニケーションを取り、理解を促すことが重要です。
リスキリングに取り組む人へのインセンティブを設けたり、業務時間内に学習時間を確保したりすることで、従業員の意欲を高めることも効果的です。全社一丸となって必要なスキルを獲得できる環境を整えることが求められます。
最後に
リスキリングは、変化の激しい時代に適応するために欠かせない取り組みです。特にDXの進展や労働市場の変化を踏まえると、従業員が新しいスキルを習得し、企業が成長を続けるためには、リスキリングの導入が不可欠となります。企業にとっては、スキル向上だけでなく、競争力を高め、持続的な成長を実現するための戦略的な取り組みといえます。
従業員にとっても、リスキリングはキャリアの選択肢を広げる機会になります。業務の効率化や新規事業の創出を支援するだけでなく、スキルの可視化や適材適所の配置を進めることで、企業全体の生産性向上にもつながります。これからの時代においては、企業と従業員がともに学び続ける文化を育て、変化に柔軟に対応できる体制を整えることが求められます。