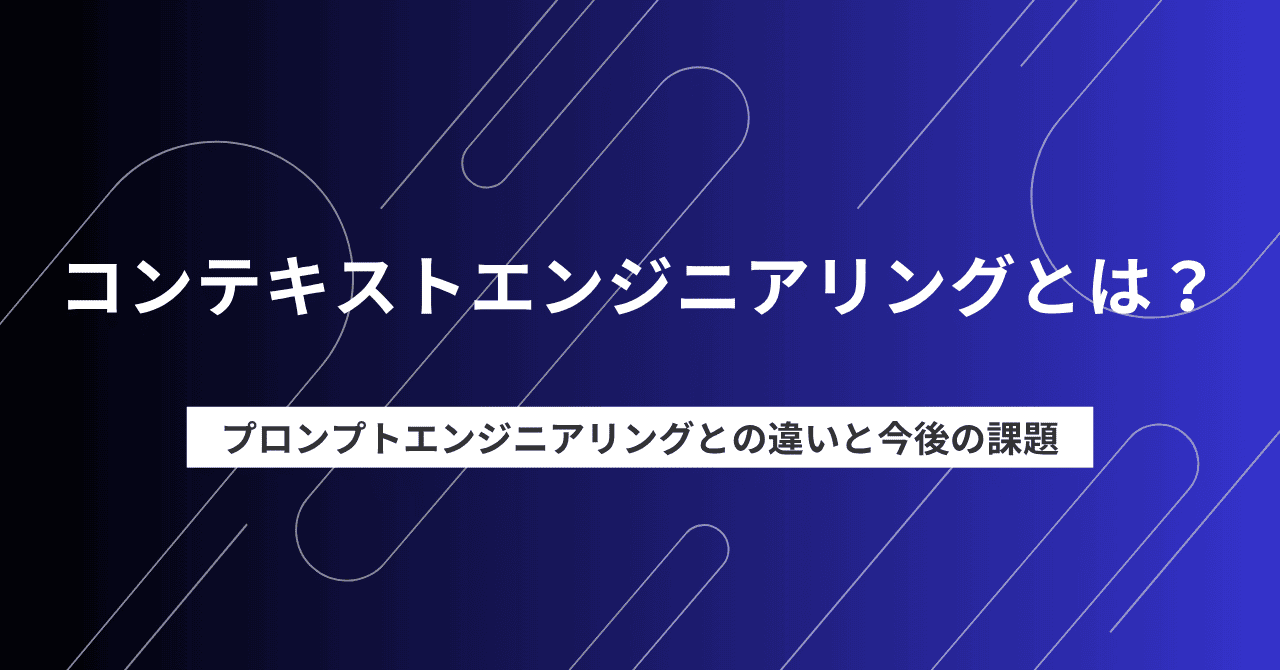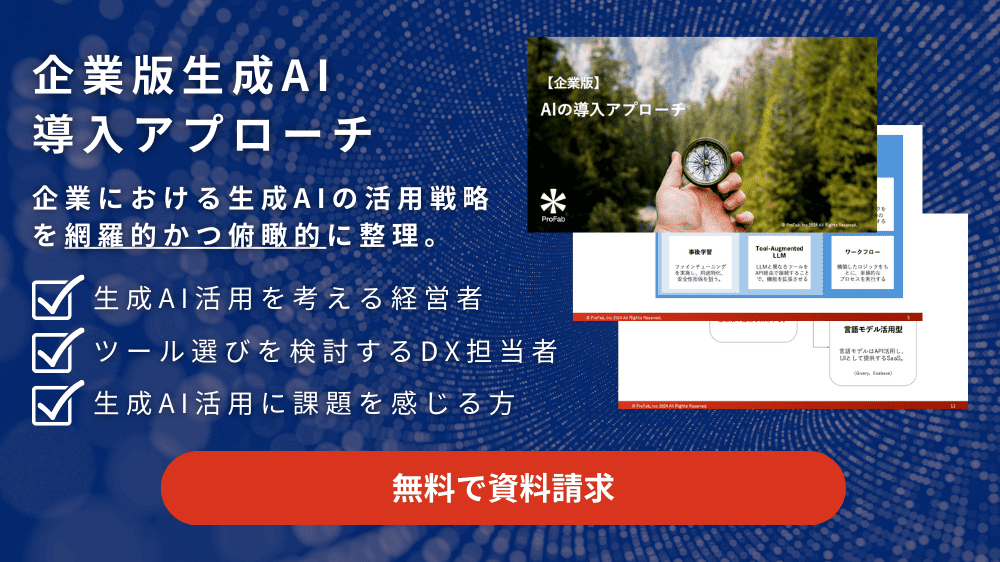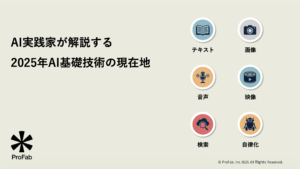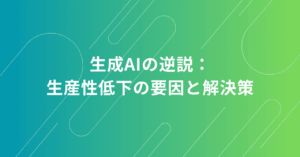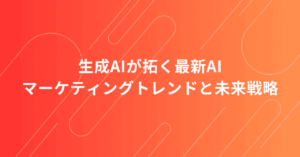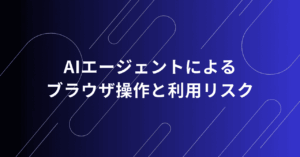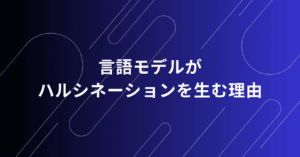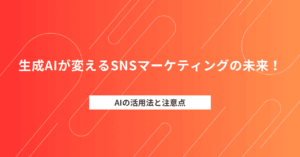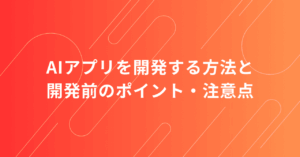コンテキストエンジニアリングとは、生成AIの能力を引き出すために、与える情報の内容や構造、順序を戦略的に設計する技術です。プロンプトだけに頼る従来のアプローチでは対応しきれない複雑なタスクや長期的な文脈管理において、ますます重要性が高まっています。
近年はAIエージェントの進化とともに、情報の取得や要約、外部データとの統合などを含めたより広範な設計手法が求められるようになってきました。AIの性能を決定づけるのはモデルそのものではなく、どのような情報をどのように与えるかという視点が、これからのAI活用において中核となります。
コンテキストエンジニアリングとは
コンテキストエンジニアリングとは、AIが適切にタスクを遂行するために必要な情報環境を設計・管理する技術です。プロンプトの工夫にとどまらず、AIの出力を正確で一貫性のあるものに導くには、文脈全体の整備が欠かせません。
2025年6月30日、Google DeepMindのフィリップ・シュミット氏はブログで「最も重要なスキルはプロンプトエンジニアリングではなく、コンテキストエンジニアリングである」と提起しました。大規模言語モデル(LLM)の性能を引き出すには、単一のプロンプトだけでなく、AIに与える前提情報全体の設計が重要とされています。
参考:https://www.philschmid.de/context-engineering
生成AIの普及とともにプロンプトエンジニアリングは広く使われてきましたが、現実の業務ではプロンプトだけで対応できない場面が増えています。シュミット氏によれば、AIエージェント開発の8割の失敗は文脈情報の欠落が原因とされます。たとえばカレンダー調整では、ユーザーの希望や優先度を考慮しないとエラーが発生しやすくなります。
AIが自律的に情報検索やツール利用、他者との連携を行うには、作業記憶に相当する適切な文脈を読み込ませる必要があります。LLMの性能が成熟してきた今、AIモデル自体の精度ではなく、情報設計の巧拙が成果を左右します。
コンテキストエンジニアリングは、どの情報を、どの形式で、どの順序で提供するかを設計する技術です。LLMの短期記憶に相当するコンテキストウィンドウにはトークン制限があるため、必要な情報を取捨選択し、構造化する力が求められます。
これは単なるプロンプト設計ではなく、AIが賢く振る舞うための環境設計そのものです。たとえばRAG(検索拡張生成)やエージェント制御などの技術を取り入れることで、ファインチューニングを行わずとも性能向上を狙えるようになります。
コンテキストの構成要素
コンテキストとは、AIが応答する前に参照する情報全体を指します。シュミット氏はその要素を以下の7つに分類しています。
- システム指示:AIの基本的な役割や出力形式を定義します。
- ユーザープロンプト:具体的なタスクや質問を与える指示文です。
- 対話履歴(短期記憶):現在進行中のやり取りの履歴です。直前の指示に応じた自然な応答を実現します。
- 長期記憶:過去の対話内容やユーザーの好み、指示された情報など、持続的に保持される知識です。
- 検索情報:RAGなどを使って外部から取得されるドキュメントやデータベース、API結果などです。
- 利用可能なツール情報:AIが操作可能な外部機能の一覧です。
- 出力フォーマット:AIがどの形式で出力するかを指定します。
上記の要素は動的に組み合わさり、1つのコンテキストを構成します。プロンプトエンジニアリングが主にシステム指示とユーザープロンプトに焦点を当てていたのに対し、コンテキストエンジニアリングでは全体を統合的に設計・管理することが求められます。
プロンプトエンジニアリングだけでは足りない理由
従来のプロンプトエンジニアリングは、LLMに短く明確な指示を与える手法でした。例として「要約して」「JSONで出力して」などが挙げられます。
しかし、実務では以下のような複雑な処理が必要です。
- 関連文書を動的に取得(RAG)
- ユーザーの状況や履歴、意図の統合判断
- テキスト・画像・音声などのマルチモーダル情報の融合
- リアルタイムな情報取得と反映
これは単一のプロンプトでは対応できず、文脈全体を管理する設計力が求められます。
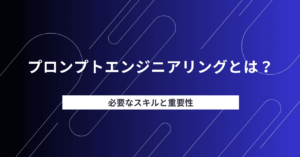
コンテキストエンジニアリングの効果
コンテキストエンジニアリングにより、AIの出力精度と実用性が大きく向上します。
- ハルシネーションの低減:RAGで外部情報に基づいた回答が可能になります。
- 複雑なタスクへの対応:段階的な処理や一貫性のある動作が可能になります。
- コスト削減:不要な情報を排除することでトークン消費量が抑えられます。
- パーソナライゼーション:長期記憶によりユーザーに合わせた応答が可能になります。
AIエージェントのためのコンテキストエンジニアリング
AIエージェントとは、顧客対応やコーディングなどの複雑なタスクを自律的に処理するボットです。単純なチャットボットとは異なり、マルチステップの処理を行い、ツールを使いこなし、セッションをまたいで情報を記憶します。こうしたエージェントにおいて、コンテキストエンジニアリングは極めて重要です。文脈設計が不十分であれば、AIエージェントは機能不全に陥ります。
AIエージェントが正確に動作するには、必要な情報を一時的に記憶領域に読み込んで処理する仕組みが欠かせません。この記憶領域には容量の制限があるため、すべての情報を詰め込むのではなく、その時点で本当に必要な情報だけを選び、優先的に配置する設計が求められます。どの情報を、どの順序で、どのように取り込むかを最適化することが、エージェントの成果を大きく左右します。
たとえば、カスタマーサポート用のエージェントが適切に対応するには、以下のような情報が求められます。
- ユーザー履歴:過去の問い合わせ内容を把握することで、重複対応を避けられます。
- ナレッジベース:FAQやマニュアルなどから正確な情報を参照できます。
- 操作ツール:CRMなどの業務システムにアクセスし、注文状況の確認などを行えます。
こうした情報が不適切に提供されると、コンテキストの混乱(誤ったツールの選択)やコンテキストの汚染(過去の誤回答の再利用)といった問題が発生します。コンテキストエンジニアリングは、関連性の低い情報を排除し、重要な情報を優先的に取り込むことで、こうしたリスクを回避します。
AIエージェントのワークフローでは、状況に応じて適切な情報を選び、順序立てて扱う設計が欠かせません。文脈の流れを制御し、不要な情報を排除しながら必要な情報を動的に更新することで、エージェントの精度と安定性が向上します。
たとえば、プログラミング支援を行うエージェントでは、単にコードを補完するだけでなく、既存のコード構造や修正履歴、開発者の書き方の傾向など、多様な文脈情報が必要となります。こうした情報を抽出・整理し、AIが理解しやすい形で提供することで、より実用的で信頼性の高い支援が実現されます。
コンテキストエンジニアリングの本質
コンテキストエンジニアリングとは、AIがタスクを達成するために必要な情報やツールを、適切な形式とタイミングで提供するように設計された動的な仕組みのことです。単にプロンプトを工夫するだけではなく、AIが本来の力を発揮できる環境そのものを構築する体系的な取り組みです。
この考え方には、次の4つの本質的な特性が含まれます。
| 文字列ではなくシステムである | コンテキストは、静的なテンプレートではなく、複数のプロセスを通じて動的に生成されるシステムの出力です。情報の取得、要約、変換、整形といった処理を経て、AIに適した形で提供されます。 |
| 常に動的に構築される | コンテキストはすべてのリクエストにおいてリアルタイムで構成されます。あるタスクではカレンダー情報が、別のタスクでは顧客履歴や外部データが必要になるなど、求められる情報は状況によって異なります。最適な応答を得るには都度適切な情報を組み合わせた文脈を用意する必要があります。 |
| 必要な情報とツールを必要なときに提供する | 不要な情報を詰め込むことはAIの性能を低下させます。コンテキストエンジニアリングでは、タスクに不可欠な知識や機能だけを過不足なく選定し、タイミングを見極めて提供することが重視されます。関連性のない情報を省くことでAIの出力の精度と信頼性が高まります。 |
| 提示の形式が成果を左右する | どれだけ有益な情報でも雑多に渡されてはAIは正確に理解できません。要点を明確に整理したサマリーや構造化された形式での提示が重要です。自然言語での曖昧な説明よりも、定義されたスキーマに基づくデータの提供の方がAIの正確な動作を引き出せることもあります。 |
上記の特性に基づくコンテキストエンジニアリングは、単なるプロンプトの工夫ではなく、AIアプリケーションを機能させる基盤そのものであり、設計思想に根ざした重要な技術領域といえます。
プロンプトエンジニアリングとの違い
プロンプトエンジニアリングとコンテキストエンジニアリングは、どちらも生成AIを活用するための重要な手法ですが、その役割とスコープは大きく異なります。前者は指示文の工夫に特化し、後者はAIが必要とする情報環境全体の設計を担います。
プロンプトエンジニアリングは、単一の命令文を工夫することに焦点を当てています。たとえば「製品の魅力を簡潔に伝えて」「箇条書きで説明して」など、AIの応答の質を高めるための言葉選びが鍵となります。短時間で明確な成果を得たい場面では有効ですが、多段階のタスクや外部との連携が必要な用途では限界があります。
一方、コンテキストエンジニアリングは、AIが何をどのように知るか、という視点から情報設計を行うアプローチです。プロンプトだけでなく、対話履歴、外部データ、ツール連携、出力形式までを統合的に設計・制御します。AIを単なる応答装置ではなく、業務に適応する知的なエージェントとして機能させるための環境整備とも言えます。
たとえば「会議を予約して」というタスクにおいて、プロンプトエンジニアリングでは形式的な応答にとどまる可能性がありますが、コンテキストエンジニアリングが施されたAIであれば、カレンダー情報や過去の傾向、チームの都合を踏まえた提案が可能になります。単発の指示ではなく、継続的な状況判断とデータ連携を前提にした設計が求められます。
以下に両者の違いを整理します。
| 項目 | プロンプトエンジニアリング | コンテキストエンジニアリング |
| 主な対象 | プロンプト文 | プロンプト+履歴+外部データ |
| フォーカス | 指示文の言い回し | 情報の流し方と管理方法 |
| 利点 | すぐに実行可能 | 長期的な安定運用、外部連携、学習継続性 |
| 必要なスキル | 論理的な文章設計 | データ構造の理解とシステム設計力 |
プロンプトエンジニアリングを入り口とするなら、コンテキストエンジニアリングはその延長線上にある応用領域です。与える情報そのものを構造的に設計する視点へと発展させることが、AIの性能を最大限に引き出す鍵となります。
コンテキストエンジニアリングの課題
コンテキストエンジニアリングは強力な手法である一方で、いくつかの課題も抱えています。中でも大きな問題は、情報の広さと情報の関連性をどう両立させるかという点です。情報量が多すぎれば、AIは無関係な詳細に引きずられてしまい、注意が散漫になります。逆に少なすぎれば、必要な判断材料が足りず、適切な応答ができなくなります。
このバランスを取るために、近年では「どの情報が重要か」を自動で判断する仕組みの活用が進んでいます。AIにとって関係の深い情報だけを選び、不要な情報は取り除くことで正確で無駄のない応答が可能になります。検索精度や文章の類似度を計算する技術を応用したもので、コンテキストを効率よく整理する手段として注目されています。
もう1つの課題は計算コストの高さです。必要な情報をリアルタイムで取得・要約し、適切な形式に整えるプロセスは、処理速度と費用の両面で負荷が大きくなりがちです。特に多数のユーザーが同時に利用する環境では、応答の遅延やスケーラビリティの問題が生じやすいため、システム設計における最適化が求められます。
今後、コンテキストエンジニアリングはさらに進化していくと考えられます。将来的には、AIモデルが自ら最適なコンテキスト形式を指定したり、エージェントが自律的にコンテキストの整合性や漏れを監査する仕組みが導入される可能性があります。また、情報の記述方式として、JSONのように汎用的なコンテキストテンプレートが標準化されることで、異なるAIシステム間での相互運用性が高まると期待されています。
コンテキストはAIの出力を変えるための新たな調整手段であり、再学習なしにAIを柔軟に制御する手段として、今後ますます重要性を増していく領域です。
最後に
コンテキストエンジニアリングは、生成AIの活用において単なる補助的な技術ではなく、出力の精度や実用性を根本から左右する重要な設計領域です。AIに必要な情報を選び取り、適切な形で整理し、最適なタイミングで提供することで、モデルの能力を最大限に引き出すことが可能になります。
一方で、情報の過不足や計算コストといった課題も存在し、今後は標準化や自律的な文脈管理機能の進化が期待されています。今後のAI活用において、コンテキストの設計力が成果を分ける大きな要素となっていきます。