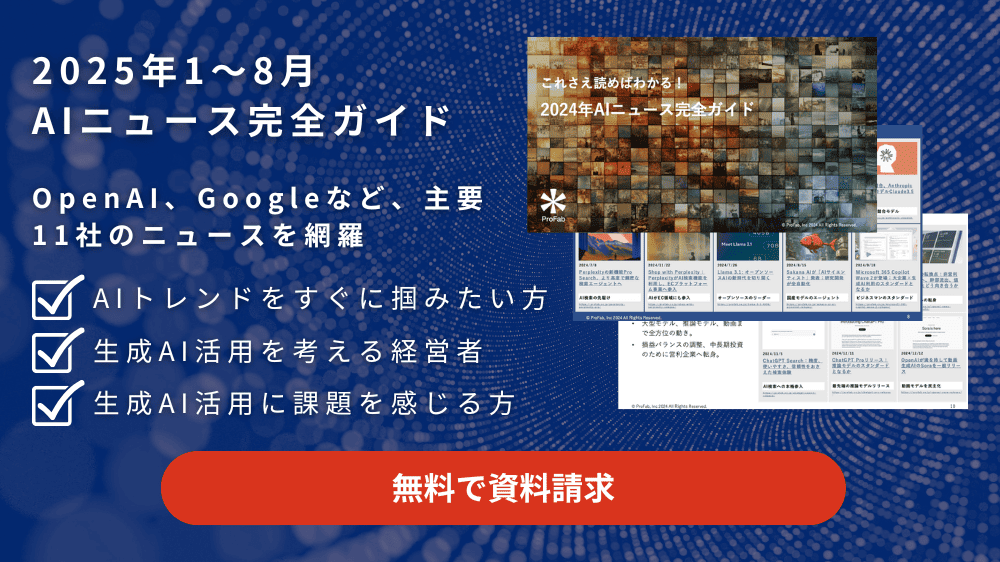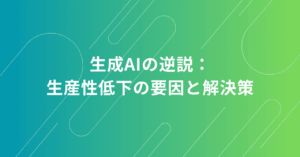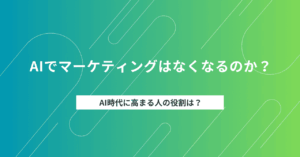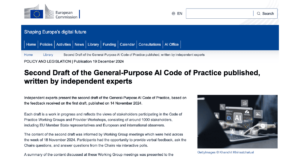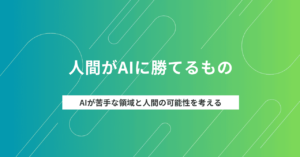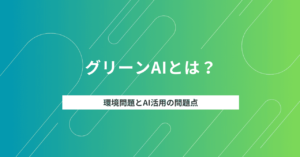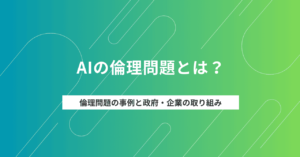生成AIの活用が広がる中、犯罪利用や偽情報拡散といったリスクへの対応が求められています。同時に、著作権の議論の中で、新聞社や声優などの団体からも法整備を要請されています。日本政府は欧州の規制メインの動きと一線を画し、政府としてはガイドラインベースの関与に終始してきましたが、これらの課題に対処するため、新たな法案を通常国会に提出する方針へと転換しました。
新法案提出の動き
生成AIは、近年急速に普及し、産業や日常生活に大きな利便性をもたらしています。しかし同時に、偽情報の拡散や詐欺の巧妙化といったリスクも顕在化しており、政府としての対応が求められています。
2024年12月26日、政府の有識者会議は生成AIに関連するリスクと法整備の必要性を指摘した報告書案をまとめ、石破首相に提出しました。この報告書では、生成AIが犯罪や国民の権利侵害に利用された場合、国が原因究明や指導を行えるよう法的基盤を整える必要性が強調されています。
石破首相はこの報告を受け、生成AIに関する新法案の作成を急ぐ方針を示しました。また、政府全体でAI政策を推進するため、閣僚全員が参加する新たなAI政策本部の設置を発表。「日本が世界のモデルとなる制度を構築する」との意欲を示しました。
新法案の内容
今回提出される予定の法案では、生成AIが関与する悪質な事案が発生した際に国が迅速に調査を行い、その結果に基づいて必要な指導や助言を行える権限を整備することが盛り込まれています。また、事業者に対しては情報提供の要請が可能となり、違法行為の抑止に向けた体制が強化される予定です。
さらに、政府は生成AIの技術革新を支援するため、研究開発の透明性を確保する制度を設けることを計画しています。これには、安全性評価方法の策定や技術開発の促進を通じて、適正な生成AIの利用環境を整えることが含まれます。
内閣府によれば、日本の規制は、事業者の自主的な取り組みを重視するアメリカのアプローチや、リスクの高いAIの利用を法律で禁止するEUのアプローチとは異なります。日本は規制と革新をバランスよく進める中間的なアプローチを目指し、世界のモデルとなる制度を構築する意向です。
「新法案」について一言
これまではガイドラインベースであった日本政府の方針が一転し、法整備へ動くこととなりました。著作権などの権利をはじめとして、早期に対応すべき事案があることは事実ですが、規制の掛け方はかなり難しい問題です。
AI利用に寛容なアメリカではOpenAI、Google、xAIのような企業の自主性を尊重する形で技術開発を進めている一方で、欧州では法的なアプローチで企業活動を制限しており、生成AIの市場シェアへの影響も大きいことが実情です。
また、日本としてはインターネット黎明期のWinny事件とIT産業への影響が思い出されます。Winny事件はファイル共有ソフト「Winny」の開発者である金子勇氏が著作権法違反幇助の容疑で逮捕された事件で、規制サイドの動きにより日本のIT産業の発展が阻害されたと解釈されることもあります。
適切なアプローチについては専門家の議論に委ねるとして、まさに「規制と技術革新のバランス」を実効性のある形で法案化していただけることを祈っておりますし、AI開発・実装については規制に抵触しない形での最適解を模索しようと思います。
出所:石破首相“生成AIで重大な問題発生 対応法案 早期に国会提出”(NHKニュース)、生成AIめぐり規制と技術革新の両立目指す新法案提出へ政府(NHKニュース)